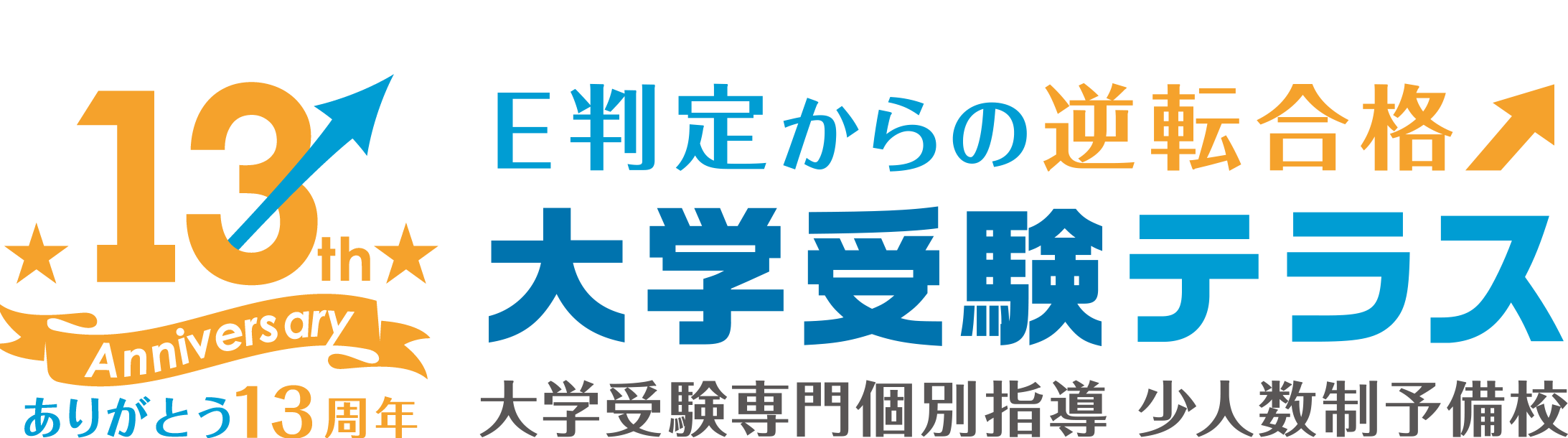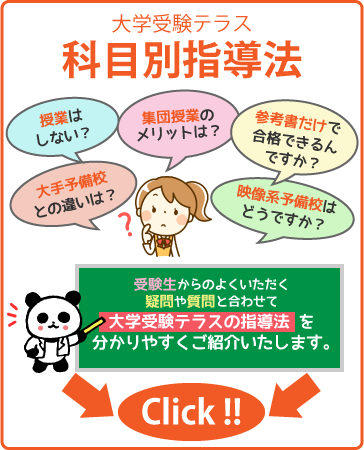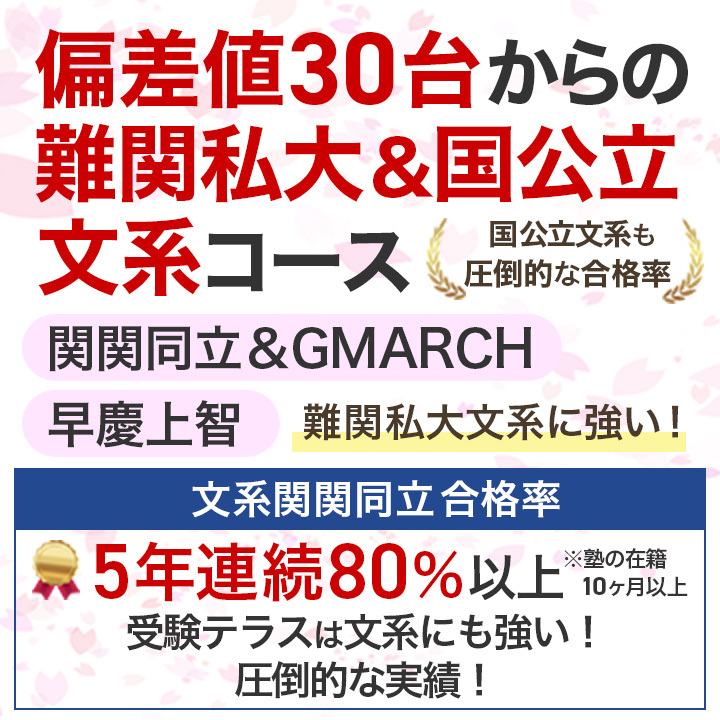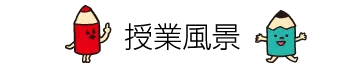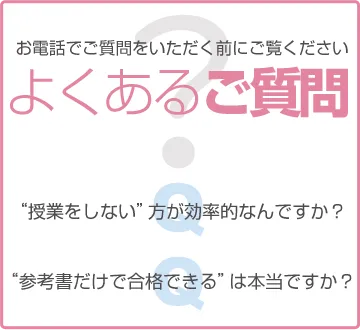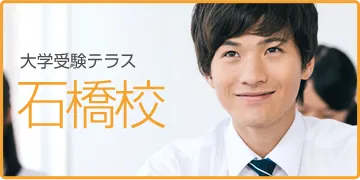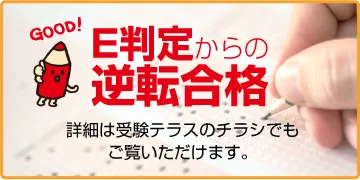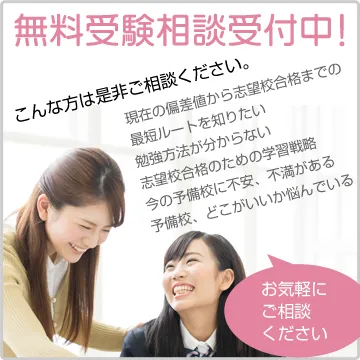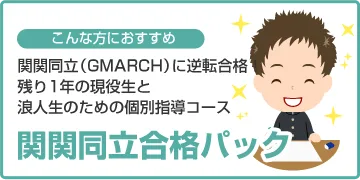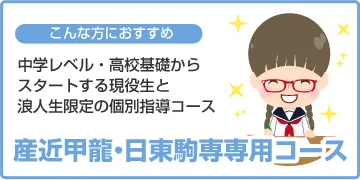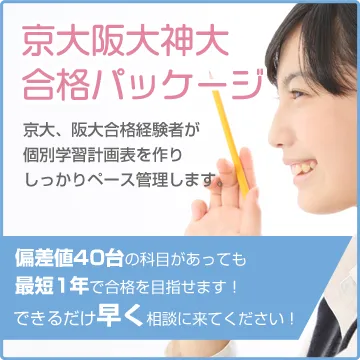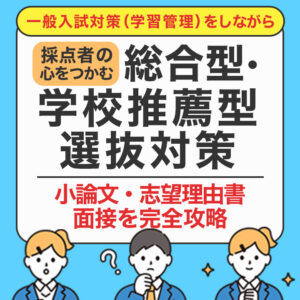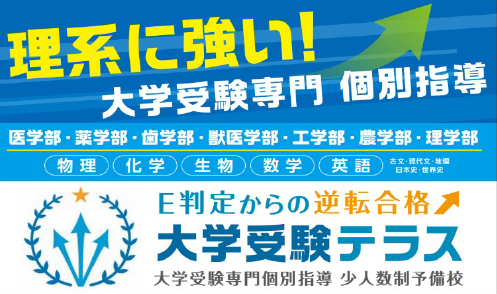国公立 獣医学部偏差値ランキング

国公立大学の獣医学部は全国に11大学しかなく、募集定員も少ないため、医学部に次ぐ難関として知られています。
ご希望の偏差値ランキング、過去3か年の倍率推移、そして各大学の特徴についてまとめました。
1. 国公立 獣医学部 偏差値ランキング(2025年度入試予想)
河合塾のデータを基準とした一般的な難易度ランキングです。
※東京大学は「理科二類」としての入学難易度です。
| 偏差値 | 大学名 | 学部・学科名 | 備考 |
| 67.5 | 東京大学 | 理科二類 | 獣医学専攻への進学は3年次(競争激化) |
| 65.0 | 北海道大学 | 獣医学部 | 旧帝大、獣医の最難関 |
| 62.5 | 東京農工大学 | 農学部 共同獣医学科 | 首都圏の国立、後期は超難関 |
| 62.5 | 大阪公立大学 | 獣医学部 | 関西唯一の国公立獣医 |
| 60.0~62.5 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 共同獣医学科 | 東海地方、後期なし |
| 60.0~62.5 | 宮崎大学 | 農学部 獣医学科 | 産業動物に強い、後期あり |
| 60.0~62.5 | 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 独自の入試方式あり |
| 60.0 | 帯広畜産大学 | 畜産学部 共同獣医学課程 | 国立唯一の畜産単科大学 |
| 60.0 | 岩手大学 | 農学部 共同獣医学科 | 東北唯一、後期なし(一部独自枠除く) |
| 60.0 | 鳥取大学 | 農学部 共同獣医学科 | 中国地方、後期なし |
| 60.0 | 山口大学 | 共同獣医学部 | 西日本の拠点、国際認証取得 |
ポイント: 偏差値60.0の大学でも、共通テストのボーダーラインは75%〜80%近く必要となるため、実質的な難易度は非常に高いです。
2. 過去3か年の倍率推移(前期・後期)
直近の入試結果(2024年、2023年、2022年実施分)の倍率です。
※「-」は実施なし、または一般枠での募集なしを示します。
※倍率は「実質倍率(受験者数÷合格者数)」または「志願倍率」の公表値に基づきます。(主に実質倍率を記載)
| 大学名 | 日程 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 傾向・備考 |
| 東京大学 | 前期 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 理科二類全体の倍率。獣医進学はさらに狭き門。 |
| 北海道大学 | 前期 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 安定して4倍前後。 |
| 後期 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 後期も人気が高い。 | |
| 帯広畜産大学 | 前期 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 共通テスト重視の傾向。 |
| 後期 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 隔年で変動あるが5倍前後。 | |
| 岩手大学 | 前期 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 比較手堅い倍率で推移。 |
| 後期 | – | – | – | 一般選抜での後期募集はなし。 | |
| 東京農工大学 | 前期 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | 倍率上昇傾向。首都圏で人気沸騰。 |
| 後期 | 15.0 | 8.1 | 8.4 | 超高倍率。定員が少なく年度により激変。 | |
| 岐阜大学 | 前期 | 4.2 | 3.2 | 4.7 | 隔年現象が見られる。 |
| 後期 | – | – | – | 後期募集なし(一発勝負)。 | |
| 鳥取大学 | 前期 | 3.8 | 4.9 | 2.9 | 2023年に急騰したが24年は落ち着く。 |
| 後期 | – | – | – | 後期募集なし。 | |
| 山口大学 | 前期 | 5.3 | 3.9 | 4.5 | 西日本の中では高倍率になりやすい。 |
| 後期 | 7.3 | 7.8 | 9.1 | 後期は難関。 | |
| 宮崎大学 | 前期 | 5.2 | 2.5 | 4.5 | 2023年の反動で24年は高騰。 |
| 後期 | 5.6 | 5.5 | 7.5 | 産業動物希望者に根強い人気。 | |
| 鹿児島大学 | 前期 | 1.6 / 23.1 | 2.7 / 16.6 | 3.2 | ※方式a(共テ重視)は低倍率、方式b(二次重視)は超高倍率の傾向。 |
| 後期 | 15.5 | 4.3 | 4.0 | 2024年に爆発的に増加。要注意。 | |
| 大阪公立大学 | 前期 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 旧大阪府立大。都市型大学として人気安定。 |
| 後期 | – | – | – | 一般選抜での後期募集はなし。 |
3. 各大学の特徴解説
国公立獣医学部は、教育の質を保つために複数の大学が連携する「共同獣医学科」システムを導入しているのが大きな特徴です。
【北海道・東北エリア】
-
北海道大学(札幌)
-
特徴: 日本の獣医学のパイオニア。「人獣共通感染症」の研究で世界的な拠点のひとつ。キャンパスが広大で、総合大学としてのサークル活動や学生生活も充実しています。
-
-
帯広畜産大学(北海道・帯広)
-
特徴: 国立唯一の畜産単科大学。キャンパス内に農場があり、牛や馬などの**大動物(産業動物)**臨床の実習経験値が圧倒的に積めます。北海道大学と共同課程を組んでいます。
-
-
岩手大学(岩手)
-
特徴: 東京農工大学と連携。北東北の拠点で、産業動物から伴侶動物(ペット)まで幅広く学びますが、特に牛の診療や公衆衛生分野に強みを持ちます。
-
【関東・東京エリア】
-
東京大学(東京)
-
特徴: 「理科二類」に入学し、教養学部を経て3年次に獣医学専攻へ進むシステム(定員約30名)。研究者育成に特化しており、臨床よりも基礎研究・アカデミアを目指す学生が多いです。
-
-
東京農工大学(東京・府中)
-
特徴: 都心からのアクセスが良く、附属動物病院の症例数が多いため、小動物(犬猫)臨床に非常に強いです。岩手大学との連携で大動物もカバーしています。研究力も高く、企業就職にも強いです。
-
【中部・関西・中国エリア】
-
岐阜大学(岐阜)
-
特徴: 鳥取大学と連携。野生動物医学や公衆衛生に特色があります。附属動物病院は東海地区の中核医療施設であり、高度な臨床教育が受けられます。
-
-
大阪公立大学(大阪)
-
特徴: 旧大阪府立大学。関西唯一の国公立獣医学部。大都市圏に位置するため、小動物臨床や最先端の高度医療に触れる機会が多いです。りんくうキャンパスは関西空港に近く、国際防疫(検疫など)の教育にも力を入れています。
-
-
鳥取大学(鳥取)
-
特徴: 岐阜大学と連携。「きのこ」や菌類の研究でも有名ですが、獣医では実験動物学や鳥インフルエンザ等の感染症研究に定評があります。
-
【四国・九州エリア】
-
山口大学(山口)
-
特徴: 鹿児島大学と連携。アジア初のEAEVE(欧州獣医学教育機関)の認証評価を受けた国際水準のカリキュラムが特徴。感染症研究センターがあり、パンデミック対策などの研究が盛んです。
-
-
宮崎大学(宮崎)
-
特徴: 畜産県である宮崎の地の利を活かし、**産業動物(牛・豚・鶏)**の臨床教育が非常に充実しています。口蹄疫などの経験から、家畜防疫のスペシャリスト育成に強いです。
-
-
鹿児島大学(鹿児島)
-
特徴: 山口大学と連携。南九州の畜産基地にあり、産業動物はもちろん、**希少動物(徳之島のアマミノクロウサギ等)**の保護や研究にも関われる独自性があります。入試で「共通テスト重視型」と「二次試験重視型」を選べるのが珍しい点です。
-
受験生へのアドバイス
国公立獣医学部は、**「後期日程がない(または定員が極少)」**大学が多いのが最大のリスクです(岩手、岐阜、鳥取、大阪公立などは前期のみ)。
-
共通テスト対策が最優先: どの大学も共通テストの配点比率が高いため、失敗すると出願先がなくなります。
-
2次試験の相性: 鹿児島大学のように試験方式が特殊な場合や、東京農工大のように英語・数学・理科の記述力が問われる場合など、大学ごとの傾向差が大きいです。
-
併願戦略: 後期日程がある大学(北海道、東京農工、帯広、山口、宮崎、鹿児島)は倍率が跳ね上がるため、実質的には「前期で決める」覚悟が必要です。